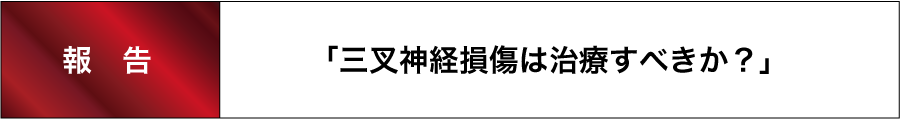2014年3月2日
コメントはまだありません
「歯科基礎医学における最新の動向」
11月15日(土)に、大阪歯科大学創立100周年記念館で、平成26年度大阪歯科学会大会・大阪歯科大学同窓会学術研修会が、大学関係者ならびに多くの同窓会員参加を得て盛況に開催された。
今回は、福島久典学会長の企画で「歯科基礎医学における最新の動向」と題し、ここ20年間での基礎歯学の変遷について、細菌学、生理学、生化学、口腔解剖学、口腔衛生学の5名の講師により研究成果を中心に発表された。
歯科医療における基礎歯学研究の重要性が改めて認識された、大変興味深く意義ある研修会となった。
細菌学研究の最新動向
メタゲノム解析により齢蝕・歯周炎の病因論は変わる
大阪歯科大学細菌学講座 准教授山中武志
ヒトの体に定着し、私たちと共に暮らす常在細菌は、一説によりますと体重のおよそ1.5kgを占めると言われています。常在細菌叢を構成する細菌の種類や、さまざまな内因感染症との因果関係につきましては、これまでに細菌培養法による詳細な検討が行われて来ました。近年この研究基盤に加え、メタゲノム解析という、細菌培養を介さずに多菌種からなる常在細菌叢の細菌遺伝子配列を個々に読取る方法が開発されました。この新手法による網羅的解析は、新たな角度から常在細菌叢と宿主との関係を探る端緒を与えてくれています。
プラーク形成メカニズムとしては、ミュータンスレンサ球菌が歯面に付着し、ショ糖を用いて不溶性グルカンを形成したところに他の多くの細菌が定着・増殖することで、プラークが成熟するというモデルが知られていますが、近年の研究では、清掃した歯面にまず最初に定着する、いわゆるイニシャルコロナイザーと呼ばれる細菌グループにミユータンスレンサ球菌は含まれないことが明らかとなっております。
ミュータンスレンサ球菌は齪蝕原性細菌ですが、鶴蝕病巣においては優位菌ではなく、鰯蝕は細菌分布の観点から乳酸桿菌優位、プレボテラ優位、レンサ球菌(ミユータンス菌以外)優位の3つのタイプに分類できることも示唆されています。
最近の知見では、歯面に初期付着する細菌として、レンサ球菌(サンギニス、パラサンギニス、オラリス、ミティス)、アクチノマイセス、ロシア、ジェメラ、ナイセリア、偏性嫌気性菌のプレボテラ、ベイヨネラが知られるようになりました。さらに、我々の研究により、イニシャルコロナイザーの多くが、ショ糖が存在しなくても菌体外に多糖を合成し、単独でバイオフィルムを形成することが判明しました。アクチノマイセス、ロシアは健康な口腔常在細菌叢の中核を成すと考えられておりますが、一方で、根尖などに感染が及ぶと、難治性のバイオフィルム感染を引き起こすことも明らかにしてまいりました。
私達が研究の目玉としておりますプレボテラ・インターメディアは、黒色色素を産生する偏性嫌気性グラム陰性桿菌で、歯周病原細菌として知られておりますが、イニシャルコロナイザーの一員として歯面に早期に定着し、マンノースを主鎖とする強固なバイオフィルムを形成します。そのマウスにおける膿瘍形成誘導は、同じ歯周病原細菌のポルフィロモナス・ジンジバーリスより100倍以上強いことも明らかにしてまいりました。唾液細菌としては口腔レンサ球菌と同程度の比率で存在すること、一部の罷蝕病巣では優位菌であること、肺炎レンサ球菌とともに誤嚥性肺炎を引起すことも示されており、常在細菌叢におけるう。レボテラの役割については興味深い新知見が蓄積しております。
口腔バイオフィルム研究が難しい理由は、すべての細菌が自然環境下で示すバイオフィルム形成性が、実験室の培養環境では瞬く間に失われてしまうことにあります。従って、臨床医と密接に連携を取りながら、「これは怪しい」と思われる臨床分離株に対して一気呵成に研究を推し進めるパワーが求められます。また、口腔常在細菌の多くは培養困難菌であり、従来の培養法のみではなかなか口腔マイクロバイオームの全容を把握することが出来ませんでした。今後は、従来の研究手法と次世代シークエンサーを駆使したメタゲノム解析を組み合わせることで、口腔バイオフイルム感染症と常在細菌についての新たな知見が得られるものと考えております。常在細菌叢の変動解析を個別に行えるようになれば、ストレス状態や口腔感染症に対するリスク評価にもつながると期待しております。
歯周組織再生療法の展望
大阪歯科大学生化学講座 講師合田征司
歯周炎により生じた歯周組織への外科的処置として切除術、組織の回復を目的とした歯肉や骨の移植歯周組織誘導法、生体材料を用いた歯周組織再生療法と進歩してきました。しかし、現状では症例によっては骨の再生は困難です。そのために歯周組織再生の研究は骨再生に注目した研究が広く行われています。歯槽骨は、骨吸収と骨形成の均衡を保ちながら再構築を繰り返しており(骨のリモデリング)、骨吸収と形成は互いに密に関連しています。よって、骨の再生を考える際にも“骨吸収”を無視することは出来ないと考えています。
現在、歯周組織再生療法に多く用いられているエムドゲインは、硬組織であるセメント質だけでなく歯槽骨の再生を認める症例も数多く報告されています。In vivoの研究においてもエムドゲインは骨芽細胞を活性化し、骨形成の指標であるアルカリフオスフアターゼ、オステオカルシン、I型コラーゲンなどの発現を増加させ、骨の再生を促進することが報告されています。
タンパク質分解酵素でありマトリックス分解酵素であるマトリツクスメタロプロテアーゼMMPsは、結合組織のリモデリングや炎症に深く関わり、骨に存在する有機成分を分解し吸収を促す酵素であります。そこでMMPsにおける骨芽細胞とエムドゲインの関連性について研究を行いました。骨芽細胞おいてエムドゲイン刺激によりMMP-1・iaMMP-3の産生が増強する結果を得ています。臨床においては、エムドゲイン単独による骨再生誘導は十分ではなく、骨移植および骨補填材の併用を必要とすることも周知の事実です。
しかし、エムドゲインと自家骨移植は、エムドゲイン単独と比較して同程度の骨再生しか認められません。そこで我々は、さらにエムドゲインが骨芽細胞に及ぼす影響を検討しました。エムドゲインは骨芽細胞の遊走能を増加ました。MMP-1は、細胞表面に存在するαインテグリンと結合すること、さらに、エムドゲインにより産生した活性化したMMPが歯周組織の主成分であるI型コラーゲンを分解することも明らかにしました。エムドゲインが骨芽細胞を活性化し骨の再生を促進しているだけでなく、骨芽細胞は産生したMMP-1と結合しI型コラーゲンの分解を促進することが示唆されました。エムドゲインと自家骨移植との併用の有用性がない理由には、エムドゲインのMMPの産生が影響を及ぼしている可能性が示唆されていることから、継続して研究を行っている現状です。
痛みとグリア細胞
大阪歯科大学口腔解剖学講座 講師中塚美智子
「グリア細胞」とは何でしょうか。グリア細胞は神経細胞とともに中枢神経系を構成している細胞で、その数は神経細胞の約10倍と言われています。「グリア」という名前の由来はギリシャ語で「糊」を表すglueです。このことが示すように、従来グリア細胞は神経細胞と神経細胞の伱間を埋める糊のようなもので、神経細胞に栄養を運んだり、軸索を絶縁して神経組織を保持したりするものと考えられてきました。しかし、近年グリア細胞には多様な神経伝達物質の受容体が発現していることが分かってきました。また、グリア細胞自らグルタミン酸やアデノシン三リン酸(ATP)などの神経伝達物質やサイトカインを遊離していることも明らかになっています。
このため、現在ではグリア細胞は神経細胞と常にシグナルのやりとりをし、脳の活動に積極的に関与していると考えられるようになりました。特に、中枢神経系における神経活動の増強にグリア細胞が一翼を担っている可能性が示唆されています。末梢神経が損傷したり、末梢の組織に炎症が起こったりするとグリア細胞が活性化し、神経活動に影響を及ぼすことが明らかになってきました。例えば、グリア細胞の1つであるアストロサイトは、細胞内情報伝達物質として重要である細胞内力ルシウムイオンの濃度を変化させ、神経細胞の電気的興菫を調節する物質を出して神経細胞の活動を調節しています。またマイクログ、リアは傷害を受けた神経細胞から出されるATPを感知して活性化し、生体内における炎症を引き起こす生理活性物質である炎症性サイトカインを放出します。
歯科分野においてもグリア細胞と痛みとのかかわりがクローズアップされ、研究が行われています。動物実験において、歯髄を損傷させた時に、延髄にある三伹神経育髄路核尾側亜核に存在するグリア細胞が可塑的変化をしていることが分かりました。三伹神経青髄路核尾側亜核は、顎顔面領域の痛みの伝達に重要な役割を果たしているとされている部位です。また我々の実験においても、口腔粘膜や咀噌筋に侵害刺激を加えた時に、三伹神経青髄路核尾側亜核に存在するグリア細胞が活性化し、その状態が1週間以上持続していました。逆にこの時、末梢側の口腔粘膜や咀I爵筋の傷および局所の炎症はこれほど長くは続いていませんでした。一方舌神経を損傷させたモデルでは、三伹神経脊髄路核尾側亜核を含めた三伹神経感覚核群においてグリア細胞の活性化がみられ、やはり活性化が1週間以上持続したと報告されています。
これらの結果より、グリア細胞が顎顔面領域の炎症性瘤痛や神経因性瘤痛、ひいては慢性痛や痛覚過敏の発現に関与しているのではないかと考えられています。今回は「痛みとグリア細胞」と題し、近年明らかになってきた瘤痛の発現とそれに係わるグリア細胞の役割など最新の知見について、我々の実験結果も含めて紹介します。
腫液の新しい役割生体情報としての唾液
大阪歯科大学生理学講座 准教授内橋賢二
唾液は口腔環境そのものであり、その質と量の良好性は口腔の正常機能の維持に重要である事は周知の通りである。唾液の分泌量は一日に1L以上とされているが、そのほとんどは口腔に留まることなく、安静時では一定時間口腔内に留まった後に、摂食時では食塊と共に消化管へ流れ込み、分泌量や組成は体性感覚、特殊感覚からの入力による反射性のものだけでなく、情動や環境変化の影響も受けやすいので同じ個体でも変動が激しい。また口腔が機能している時の唾液は採取することが困難なので、研究を進めるうえにおいて留意すべき点は多岐にわたる。
唾液は腺房部細胞で生成され口腔に供給されるが、その原材料は水を含め血漿由来物質である。唾液成分には血漿由来物質が、「腺組織をそのまま通過したもの」あるいは「腺細胞で合成されたもの」があり、酵素やホルモンなど様々な高分子物質を含んでいる。とくに、量的にはわずかであるが、糖タンパク質および高プロリンタンパク質は歯や口腔軟組織の保護・円滑機能を有し、さらに血漿由来および唾液腺細胞由来の抗菌因子も多種含み、口腔機能の維持のみならず免疫機構においても重要な役割を果している。
このように唾液の生理的役割についての研究が進む中、歯科臨床分野では唾液によるスクリーニングテストが古くから試みられ、チエアサイドでの蛎蝕リスク検査や歯周病の進行度の診査検体としても、その応用が確立されているものも多数ある。一方、最近では唾液プロテオーム(全蛋白質解析)の研究が盛んに行われ、口腔疾患の診断や客観的な治療評価が可能になることが示唆されており、非侵雲性に採取できる唾液によるスクリーニングテストが血液に代る有力なバイオマーカーとして認知され、その応用範囲が拡大しつつある。
現在、唾液中に出現するバイオマーカーとして実用されているものには、HIV-1抗体、HAV抗体、HBSAG抗体、GIucoSe,Helicobacter pylori抗体、各種腫瘍マーカーなどがある。また唾液中コルチゾール、ラクトフエリンおよびアミラーゼは精神性ストレスのバイオマーカーマーとして注目をあびており、唾液は様々な疾患の診断およびリスクファクターを知る手がかりになる可能性がある。
以上のように、唾液成分の分子化学的解析から唾液の応用が多岐にわたり、重要な役割を担えることが分かってきた。今後は簡単に採取できる「バイオマーカーとしての唾液」による多種多様なスクリーニングテストでの応用が拡大され、さらにそれらのデータ蓄積が進めば、病変の早期発見・治療に貢献できる可能性が大きい。
初期齲蝕の診査・定量法について
大阪歯科大学口腔衛生学講座 講師土居實士
近年、欧米諸国や我が国においても齲口のの罹患状態が減少しており、2011年歯科疾患実態調査では、3歳児の一人平均齲蝕経験歯数は0.7歯、12歳児では1.4歯に減少しています。齲蝕減少の背景には、フッ化物応用の普及や口腔保健行動が普及・定着したことなどが報告されていますが、齲蝕の発生・進行プロセスが明らかにされたことが最も大きな要因であると考えられます。しかし、Pittsは、一人平均齲蝕経験歯数で表わされる齲蝕は減少しているが、臨床的に検出される齲蝕は氷山の一角であり、水面下に存在する潜在的な齲蝕(初期齲蝕)を検出・管理することが重要であると提唱しています。しかし、臨床や多くの疫学調査では、実質欠損や治療痕の有無等から齲蝕経験によって齲蝕の罹患状態が表現されており、初期齲蝕の状態を診査する方法ではありません。
現在、初期齪蝕の診査方法は視診と機器による診査の2つに分類されます。
International Caries Detection and Assessment System (ICDAS)齲蝕発生・進行プロセスに基づいて視
診によって歯を診査し、検出された初期露蝕の活動性を評価する新しい診査方法です。つまり、従来の齲蝕経験に基づく診査に加えて、歯面の状態をコード0:健全、コード1:歯面乾燥後に検出される齲蝕によるエナメル質の色調変化(白斑など)、コード2:歯面乾燥前に検出される齲蝕によるエナメル質の色調変化、コード3:表層下脱灰の表層が崩壊したが、脱灰深さがエナメル質に限局、コード4:齲蝕による象牙質の色調変化がエナメル質を透けて検出、コード5:齲窩の大きさが歯冠の半分以下の象牙質に達した罷蝕、コード6:齲窩の大きさが歯冠の半分以上の象牙質に達した齲蝕、のように、齲蝕発生・進行プロセスに伴った診査を行い、コード1以上の歯面に対して齲蝕活動性をActiveとInactiveの2段階に診査する方法です。
一方、機器による方法は光学的な方法を用いて診査を行います。つまり、光またはレーザーを歯面に照射し、照射された光やレーザーによって生じた反応や光の透過性を画像化・数値化することによって初期齲蝕を検出・定量します。Quantitative Light-induced Fluorescence(QLF)法は初期齲蝕の検出・定量機器の1つで、歯の表面に冑紫色の光を照射することによって生じた歯の蛍光像をデジタル画像として保存し、画像解析から初期齲蝕の検出と定量を行う方法です。
今回、我々の講座で取り組んできたICDASやQLF法を用いた基礎研究、フッ化物配合歯磨剤やCalcium Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate(CPP-ACP)、緑茶由来のフッ化物配合チユーイングガムの摂取が初期齲蝕に及ぼす影響などについて、行ってきた研究成果や初期齲蝕の検出・定量法の問題点などについて報告する予定です。